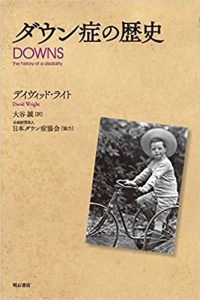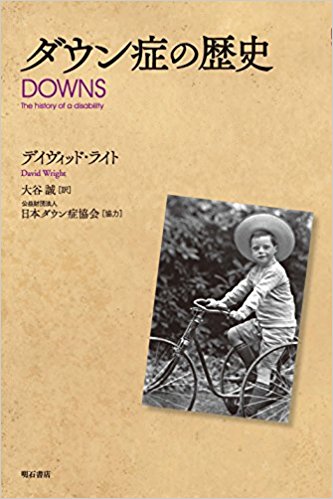先導的人社ワークショップ プログラム
日時 2016年9月2日(金)、9月3日(土)
場所 慶應義塾大学 日吉キャンパス 独立館 D-305教室
9月2日(金)
10:00~11:30 医学史のアウトリーチについて
鈴木 晃仁(慶應義塾大学 経済学部 教授)
13:00~14:30 沖縄長寿説の成立と展開―水島治夫『<公刊前>1921-25年分府県別生命表』を発端として―
逢見 憲一(国立保健医療科学院 生涯健康研究部 主任研究官)
14:30~16:00 日本の看護婦の歴史 ー看護婦として働くということー
山下 麻衣(京都産業大学 経営学部 教授)
16:00~17:30 「医制」再考–明治初期医療・衛生政策の再検討の一環として–
尾崎 耕司(大手前大学総合文化学部 教授)
9月3日(土)
10:00~11:30 病者の文学を軸としたハンセン病問題啓発のための模索
佐藤 健太(疾病文学の編集者)
午後 東京都立松沢病院リハビリテーション棟1Fにて行われる「私宅監置と日本の精神医療史」展見学及びギャラリートーク。同病院内の日本精神医学資料館を見学。

<画像をクリックで拡大>
2016年9月2・3日に慶應義塾大学日吉キャンパスで、第一回目のワークショップが開催されました。4人の報告者のほかに、出版関係者、海外からの研究者、アーティストなど、多様な領域からの参加者がつどいました。
学術研究とその成果を研究者のコミュニティの中でとどめるのではなく、コミュニティの外へも発信し、相互にコミュニケートし、新たな世界を創造することは、人文社会科学では近年ますます重要になっているテーマです。このテーマに医学史でどのように取り組むのか。研究会では各報告とその後のディスカッションを通じてこのことが検討されました。
まず、4人の報告者に先立って、プロジェクト代表者である鈴木晃仁(慶應義塾大学)が、「アウトリーチ」というキー概念を使って、イギリスにおける取組を例に、ワークショップの狙いとプロジェクトの目標とを素描しました。とくに、ウェルカム・ライブラリーをはじめとするイギリスの医学史研究の拠点における膨大な所蔵資料群(書物などの出版物、手書きの資料群、絵画や標本、医療器具・機器などの収集物)の公開・展示や、ワークショップに参加したアーティストの飯山由貴氏と鈴木との共同作業を例にした医学史と芸術とのコラボレーションが紹介されました。そして、鈴木は、こうした展開が可能になるには、医学史研究の一層の深化と、医学史研究者コミュニティと他の領域とのネットワークの構築とが必要になることを強調しました。
【参考:ブログ記事・医学史のアウトリーチについて /鈴木 晃仁(慶應義塾大学)】
続く4人の報告では、現在の日本医学史研究の最新の到達点が示されるとともに、その「アウトリーチ」の可能性が議論されました。
まず、自身が医学部で医学を修めた後、公衆衛生学や人口などの保健衛生統計という、医学の中でも社会領域に近接する領域や医学史、歴史人口学で旺盛な研究活動を行っている逢見憲一(国立保健医療科学院)が、「沖縄の人は長寿である」という言説の裏付けとして引用される沖縄県の人口統計―1921-1925年分府県別生命表―について、とくにその成立過程に注目して報告しました。逢見は、この生命表を作成したのが、日本の生命表研究の草創期を支えた水島治夫とその研究グループであったこと、そして彼らの調査では乳幼児死亡と高齢者死亡とが他県に比べて低い値を示したことを明らかにしました。その上で逢見は、水島と彼のグループが、沖縄県では出生届や乳幼児の死亡届がもともと厳密に行われていたわけではなく、乳幼児死亡の統計の精度に疑義があることを認識していたこと、しかし、一度、統計が公になった後、水島たち自身の批判は忘れられ、「沖縄県=長寿県」という言説の再生産にこの統計が今日まで利用され続けていることを明らかにしました。この報告は、科学研究とその成果が、一度公にされると、それらが流通する過程で、研究や成果もつ意味や問題点は顧慮されず、時には誤解さえされて利用されるということをも示唆しています。
次に山下麻衣(京都産業大学)が、経済史・労働史の立場から、自身が長年取り組んでいる近代日本の看護婦の歴史研究の中で、現在では見られない「派出看護婦」を詳細に検討しました。まず、派出看護婦は、看護婦によって組織された派出看護婦会に所属し、そこから派遣される看護婦のことを指していること、明治から昭和前期では、とくに大都市部において、派出看護婦は看護婦の中でマイナーな存在ではなく、むしろ非常に多くを占めており、看護婦養成で重要な位置を占めていたことを示しました。給与も当時の主な女性の職業と比較しても悪くなく、伝染病の定期的な流行時の看護や(大)病院での入院患者への様々なケア、裕福な家庭の自宅療養(介護?)支援など、常に需要があったこと、また需要の多様性故に、年齢が高くても働くことができ、とくに都市部の女性にとって、自分が女性として、女性である自分のために働くことができる職業として魅力的であったことが描かれました。他方で、医学や看護についての高い専門性が必ずしも必要とされなかったために、昭和に入ると東京府の無資格の病産婦付添婦(病気やお産の女性のための家政婦のようなもの)や、内務省による無資格の派出婦に近い看護婦の准看護婦のような、派出看護婦と似た労働を行い、さらに単価が派出看護婦より安い職種が出現して競争が激化したこと、そして戦時中には看護婦志望者そのものが激減したことによって、派出看護婦は減少から消滅への道をたどったことが明らかにされました。そして戦後の日本の看護がアメリカの影響下で科学に基づいた看護とそのために育成される看護士を標榜したために、派出看護婦は、戦後の看護学会や看護士界によって、非科学的な看護士であり、乗り越えられなければならなかった存在というスティグマを刻印され、正当な歴史研究がなされないまま今日に至っていることが報告されました。
山下による経済史・労働史からの医学領域へのアプローチに続いて、尾崎耕司(大手前大学)が近現代日本史研究から医学・衛生領域への接近を試みました。この報告は、近代日本の医療・医学教育・薬事の基礎を築いた法律とされる「医制」作成過程と、そこで誰・どのグループが中心的な役割を担ったのか、これまでの「医制」の内容について見落とされている領域―司薬場の管理と薬品・剤の輸入規制―について、「医制」の原案や作成にかかわった人たちの書簡、維新政府の文書などの一次史料を一つ一つ組み合わせながら読み解くものでした。「医制」作成を誰・どのグループが担ったのかについて、長与専斎による、乃至は彼の前に医療・医学行政に携わっていた相良知安とそのグループが作成したものを知安らが失脚後、専斎がほぼそのまま引き継いだといった従来の考え方が紹介され、そのどちらもこれまでの研究や一次史料との齟齬があることが指摘されました。そこで、報告では、改めて「医制」やそのもととなったとされる「医制略則」についての当時の史料での記述を詳細に検討するとともに、相良や長与たちが維新政府内でそれぞれ当時の立場の変化が明らかにされました。それらから、「医制」はこれまでの考え方とは違って、相良知安とそのグループがその原案から成案までを作成していたとした。また、「医制」の中の医学校についての条文と当時の医学校の開設・拡大をめぐる維新政府内の動きの分析からも、相良らが「医制」作成の中心であるというテーゼが補強されました。さらに、従来「医制」の医学・衛生・医師養成の側面ばかりが注目されてきたことに対して、本来「医制」作成の発端となった薬事領域の重要性を強調し、司薬場設置や当時問題となっていた薬用アヘン輸入の管理・取締を巡る政府内の動きなど、従来見過ごされてきた問題に初めて光を当てています。そして、全体として、「医制」を巡って医学界で相良らのグループと長与らのグループとの緊張関係があったこと、最終的に長与らが「医制」発布後医学界でのイニシアチブを握り、その後の明治期の医学・薬事をはじめとする様々な領域で影響力を増していったことを私たちに示しました。医学史とは疎遠に見える政治の領域が医学と密接に関係していたこと、日本近代史研究が培ってきた手堅い史料批判が医学史研究に大きな恵みをもたらすことを示した報告でした。また、この報告は、佐賀県立文書館の相良家文書や国立公文書館所蔵の文書などがインターネット上に公開され、いままで利用が難しかった史料群へのアクセスが格段に容易になったことで可能となった研究の好例ともいえるでしょう。
これまでの3つの報告は、歴史研究者が自らの分析視角から医学領域へとアプローチし、医学が医学以外の領域との関係性の中で存在していることを、過去の事例から丁寧に読み解いていると見ることができます。
それに対して、2日目の佐藤健太(疾病文学編集者)の報告は、ハンセン氏病をフィールドに、この病の患者自身が執筆した小説などの作品群、ハンセン氏病についての研究、ハンセン氏病に取材した映像作品などのハンセン氏病に関係する様々な「テクスト」や、ハンセン氏病患者が収容され現在は一般にも開かれている療養所や国立ハンセン氏病資料館といった「ハコ」や「モノ」を媒介項として、ハンセン氏病患者とその家族や支援者、医療関係者、ハンセン氏病に多少は関心のある人たち、この病気について全く何も知らない人たちをどのようにつないでいくのかを、自らの編集・出版や実践の経験に基づいて検討したものでした。その中でも、患者たちによる膨大な数の長短さまざまな小説群を、ハンセン氏病の患者さんとともに読む読書会(「ハンセン病文学読書会」)は、参加者が患者自身の綴った言葉を頼りに患者の生活世界へと入り込み、よくわからない部分は会に参加している患者さんに直接質問し、参加者が作品を自由に論じ合うことでハンセン氏病とその患者、そして彼らの生活世界への理解を深めていく場として機能しているように思いました。また、佐藤が手掛けた豊島区立図書館でのハンセン氏病をテーマにした文学・映像作品と研究を紹介する展示は、この病気のことを何も知らない人たちに、この病気への関心をもってもらうための入り口を作る試みとして見ることができるでしょう。ただし、この入り口を通った人たちがその後どこへ向かえばいいのか、彼らが方向を探そうとするときの案内役となるようなものがまだ十分とは言えないのかもしれないという印象も残しました。例えば、「ハンセン病文学読書会」のような会にどうやってたどり着けるのか、また、そのような会を開きたい人たちがいるときに、彼らは何を参考に会を開けばいいのか、そうした人たちのためのガイドとなる仕掛けをどのように構築するのかが、ハンセン氏病をめぐる豊かなテクスト群の「アウトリーチ」のための課題の一つではないかと思われます。
佐藤報告の後、2日目は、愛知県立大学の橋本明教授が取り組んでいる移動展「私宅監置と日本の精神医療史」を東京都立松沢病院で見学しました。当日は橋本先生自身による展示の説明を伺うことができました。展示は、私宅監置(精神病の患者を自宅で監禁する制度)について、その起源(江戸時代の江戸で見られた「檻入」)から明治33年(1900年)の精神病者看護法によって制度として法的に確立され、昭和25年(1950年)の精神衛生法による廃止、そして廃止後も見られた違法な監置までを豊富な文書史料と写真資料とによって描き出していました。これによって、現在の日本の精神医療が入院医療中心となっていて、患者の地域生活を支援する方向への転換がなかなか進まないことの源流をたどっていくと私宅監置にたどり着くのではないかという問題提起がなされていました。展示を見ながら、一つ一つの史料や写真が読む・見る側へ訴えてくるエネルギーに圧倒されるとともに、医学史研究の成果を「アウトリーチ」するための選択肢として展示のもつ意義を感じました。
私宅監置の展示は、自身も精神科医である橋本先生による研究の成果を示すという側面もありました。この展示の後、ワークショップ参加者は、会場となった都立松沢病院に併設されている「日本精神医学資料館」で別のタイプの展示を見学しました。

<画像をクリックで拡大>
【参考:ブログ記事・東京都立松沢病院での「私宅監置と日本の精神医療史」展-企画・展示者としての舞台裏からの報告- /橋本明(愛知県立大学)】
この資料館は、1919年の開院後に都立松沢病院に残された様々な文書資料、患者自身が創作した絵画やスクラップ、治療設備や監禁・拘束のための道具、そして実際に使用されていた病棟からなる資料館で、日本の医学史関係の資料館の中でも一級のものといっていいでしょう。また、昭和35―40年ころの松沢病院の様子を記したドキュメンタリーフィルムが残されており、それも鑑賞しました。当時の患者の作業療法の様子などは、1920年代のドイツの精神科医ヘルマン・ジーモンが行った治療法を彷彿とさせるものでした。展示の中には、「葦原将軍」と自らを名乗っていた患者についての展示や、ある一人の精神患者の手による『画集』と名付けられた非常に大部なスクラップブックといった、それぞれが異様なエネルギーを放つとともに、医学史や精神医学はもちろん、美術や文学といった領域の人たちにとっても非常に興味深いものがありました。
しかし、その内容の無尽蔵とさえいえる豊富さとは対照的に、これらを保存・展示するための体制は貧弱としかいえない状態でした。イギリスやドイツであれば、医学史の専門家が入り、病院と連携しながら資料館を維持・充実させる体制をとることができるかもしれません。しかし松沢病院では、これらの史料・資料群を扱う専門家はおらず、病院の医師や職員が手探りの状態で管理していました。展示の設備も貧弱であり、史料の保存という観点からみても良好とはいいがたいものでした。これらの史料・資料群は、歴史家にとってだけではなく、医師、そしてこれから精神医学を志す医学生にとっても興味深いもののだと思われます。これらをどのように保存・展示していくのかについて、医学史家のみならず、さまざまな人を引き込んで議論、実践する必要があるでしょう。
医学史は、ともすれば医師で歴史に興味のある人たちが趣味的にやるものとか、歴史研究の中でも特殊な領域としてみられることが多いのかもしれません。しかし、今回のワークショップの3人の研究者たちによる報告は、医学史研究は決して特殊で閉じた領域ではなく、さまざまな領域の歴史研究者が独自のアプローチで接近し開拓できる豊かな領域であることを明確に示しています。医学史の専門家を自認する人々だけではなく、歴史研究者で医学には素人である人々との交流を盛んにし、医学史研究をより開かれたものとすることが医学史の「アウトリーチ」に必要であることを今回のワークショップは示唆しています。
と同時に、医学史を「アウトリーチ」することだけで満足してしまう―医学史の「アウトリーチ」を最終目的としてしまう―ことは避けねばなりません。佐藤報告にみる、ハンセン氏病をめぐる様々なテクスト群を活用した患者、この病気に関心のある人・ない人をつなげていく試み、橋本明氏による私宅監置についての巡回展示、都立松沢病院にある「日本精神医学資料館」は、それぞれ医学史の成果によりながら、医学史家、患者、医師をはじめとする医療関係者、医学に関心のある人・ない人をつなぐ場を作り出そうとしていると考えることができます。「アウトリーチ」はそうした場をつくるためにこそ行われなければならない、そのように考えることが重要ではないでしょうか。そうした場を作り、そして失わないためにも、これらの人たちの共同作業を必要とする時が必ず来るでしょう。さもなければ、「日本精神医学資料館」のような医学的にも貴重な資源が消失してしまうかもしれません。
このワークショップと研究プロジェクトは、こうした悲惨な未来ではなく、医学・医療関係者、医学史家、患者・家族・彼らを支える人たち、人文社会科学者、理系の研究者、作家、アーティスト、メディアの人たち・・・ほんとうに様々な人たちが集う場を医学の歴史を中心にして作るための準備作業になっていくことが望まれます。